三焦、包絡、命門弁
《類経附翼》より
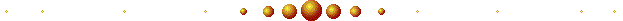
客があり、問うて言われました。三焦包絡命門は、医者の要領、臓腑の大綱です。しかし、あるものはそれに形があるといい、あるものはそれに形がないといい、あるものは三焦包絡は表裏をなしているといい、あるものは三焦命門は表裏をなしているといい、あるものは五臓にはそれぞれ一つあるがただ腎にだけ二つあるとして、左を腎とし右を命門として、命門は男子にあっては精を蔵し女子にあっては胞にかかるとしています。これらの論に対して、疑問を持たないことはできません。多くの論があるにもかかわらず議論が定まっておりません。理に二つはないはずなのに、どうしてこの混乱を是とすることができましょう?結論としてこの問題もまた一つにまとまることがあるのでしょうか?
私は答えて言いました。あぁ!医道は、軒岐〔伴注:黄帝と岐伯〕より始まっています。軒岐の言葉は、霊素〔伴注:霊枢素問〕に明らかにされています。霊素の偉大なこと、精確で遺漏がありません。その論ずる所はそもそも必ず理から発しており、その名が付けられている所は、必ず形から生じています。ですから内経の文には、その字句においていいかげんなところや空論はありません。後世においてこれを受け継いだものに、どうして霊素の範囲を逸脱したものがありえましょうか?現代における混乱の原因は、つまりは、難経から始まっているものです。難経は霊素を敷衍して作られたものとして、諸家にもっとも先んずるものであるため、そこには多くの誤りがあり、ついには後世に混乱を生ぜしめてしまいました。〔伴注:難経の〕三千年来の伝承にあえて逆らいたくはありませんが、後世おこるであろう疑問に対して解答を示しておく必要があるでしょう。三焦心包絡の問題を先ず解き明かし、順次その他の事柄について述べてみたいと思います。
三焦は五臓六腑の総司であり、包絡は少陰心主の護衛です。《二十五難》には、『心主と三焦とは表裏をなし、ともに名前はありますが形はありません。』とあります。しかし表裏という言葉を使うのであれば、これに形がないとするのは問題があります。そもそも名前というものは形があってはじめてそれに対してつけられるものなのですから、名前はあるが形はないと断ずることは《内経》に言う空論に属すると言わなければなりません。王叔和〔伴注:三世紀:《脉経》の著者〕や啓玄〔伴注:王冰:七世紀末:《内経》の注釈者〕以下はみな、この言葉を宗〔伴注:大本〕としてそのまま、三焦には形はなく名前だけがあると語ってきました。この二人が明確にできなかったことを、どうして後の人々が明確にできるでしょうか?
しかし、徐遁、陳無択に至って始めて三焦に形があるということが言い出されました。『脂膜は掌のような大きさであり、正に膀胱と相い対します。二本の白い脈が中から出、背を挟んで上り、脳を貫きます。』と。
私はこれによって、両経〔伴注:素問霊枢〕をすべて考えてみました。《霊枢・本輸篇》には、『三焦は中瀆の腑です。水道が出ます。膀胱に属し、孤の腑です。』とあります。また《本臓篇》には、『腠理が密で皮膚が厚いものは、三焦膀胱も厚く、腠理が粗で皮膚が薄いものは、三焦膀胱も薄い』とあり、これは、緩・急・直・結の六者それぞれにも区別がされています。《論勇篇》には、『勇士は、その眼睛が深くしっかりし納まり、眉が長くしっかりとたっていて、三焦の腠理も充実しています。』『怯士は、その眼睛が大きくて納まりが悪く、びくびくと乱れており、三焦の腠理も緩んでいます。』とあります。《決気篇》には、『上焦は開き発することによって五谷の味を宣し、皮膚を薫蒸して全身を充実させ、毛にツヤを与えます。これは霧露が注がれるような状態であり、これを気と言います。』『中焦は気を受けて汁を取り、変化させて赤くします。これを血と言います』とあります。《営衛生会篇》には、『営は中焦から出ており、衛は下焦から出ています。』さらに『上焦は胃の上口から出て食道を上行し、隔膜を貫いて上り、胸中に散布します。』『中焦もまた胃中に合してあり、上焦の後ろに位置します。・・・(中略)・・・糟粕をさり、津液を受け、その精微を化して、上に肺に注ぎます。そこで化して血となり、全身を養います。これはとても貴いものです。そのため血だけが経脉の中を流れることができるのです。名づけて営気といいます。 』『下焦は回腸から別れ、膀胱に注いで滲み入らせます。ゆえに水穀は胃の中に貯えられますが、消化されるに従って糟粕ができ、それが下に大腸に運ばれます。これが下焦の主要な機能となります。』さらにまた、『上焦は霧のようであり、中焦は漚のようであり、下焦は瀆のようである』とあります。《素問・五臓別論》には、『胃・大腸・小腸・三焦・膀胱、この五者は天気によって生じたものです。その気は天に象りますので、瀉して蔵することがありません。』とあります。《六節臓象論》には、『脾・胃・大腸・小腸・三焦・膀胱は倉廩の本であり、営の位置する場所です。』とあります。
心包絡については、《霊枢・邪客篇》に、『心は五臓六腑の大主であり、精神の宿る場所です。その臓は非常に堅固なため、邪を受け入れることが出来ません。これを受け入れれば心が傷られ、心が傷られれば神が去り、神が去れば死にます。ですから、諸邪が心にあるというのはすべて、心の包絡にあるものなのです。』とあります。
これらがおよそ経の言わんとしているところのものです。もし無形であるというのであれば、どこを通って水道が出るのでしょうか?また何が厚・薄・緩・急・直・結に分けられるのでしょうか?またどこに縦〔伴注:緩んでいる〕といい横〔伴注:充実している〕といわれる腠理があるのでしょうか?また何を霧・漚・瀆のようであるとするのでしょうか?気といい血という区別はどこにあるのでしょうか?
心主も無形であるといいます。心に代わって邪を受けるものが心の包絡です。もしその形がないのであれば、どこでこれ〔伴注:邪〕を受けるというのでしょうか?これらの経文には見るべきものがないのでしょうか。
《難経》は《内経》の難を発し明らかにしたものなので、《難経》といいます。ですからこの《難経》は実に《内経》から出ているものです。今見てきましたように、《内経》ではその名状が詳細に説かれていますが、《難経》ではこれを無形としています。《難経》の無にしたがうべきでしょうか?それとも《内経》の有にしたがうべきでしょうか?
また、徐遁〔伴注:不明〕、陳無択〔伴注:十二世紀の人〕の二人は、三焦の形について述べて、腎の下の脂膜であるとしていますが、もしそうであるならば、なぜ三という名前が付けられているのでしょうか?またどうやって上・中・下に分けるのでしょうか?どうしてそれを腑であるというのでしょうか?さらにはこれらの説は何を根拠としているのでしょうか?これらもまた経にはないものであると言わなければなりません。
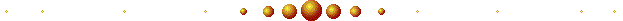
客が言いました。心の包絡については、その文〔伴注:名前〕においても義〔伴注:意味内容〕においてもかなり明快で、古今の諸賢は歴代、それを指して、心を裹む膜であるとしていますが、これは疑いないところでしょう。しかし三焦については、今、有形であることを言われ、さらに徐遁、陳無択の論を退けられています。それでは果たしてどのようなものであると考えられるのでしょうか?
いわく:ただ字義によってこれを考えてみればこと足りるのではないでしょうか。三とは三才を象り、際上極下〔伴注:上の際みから下の極みまですべて〕という意味です。いわゆる焦とは火の類に象ったものです。色が赤く陽に属するという意味でしょう。人の身体というものは、外の皮毛より、内の臓腑にいたるまで、その腔腹の周囲にある上下の全体、大きな袋状のものは果たして何なのでしょうか?その内側の一層めは,色は真っ赤で、その象は六合〔伴注:天地四方の六方向、すなわち占有空間の全体〕のようであり、諸陽を総括して護っています。これが三焦でなくてなんなのでしょうか?
《五癃津液別論》には、『三焦は気を出し、肌肉を温め、皮膚を充実させます。』とあります。ここでは、肌肉の内側、臓腑の外側を三焦としていることは、すでに明らかになっています。また《背兪篇》では、『肺兪は三焦の間にあり、心兪は五焦の間にあり、膈兪は七焦の間にあり、肝兪は九焦の間にあり、脾兪は十一焦の間にあり、腎兪は十四焦の間にあります。』とあります。これは躯体を焦と呼んでいるのではないでしょうか?虞天民〔伴注:虞摶:一四三八年~一五一七年〕は、『三焦は腔子を指している言葉です。総じて三焦といいますが、その体は腔子の内にある脂膜にあり、五臓六腑の外側を包羅しています。』と語っていますが、この説はこれに近いものです。けれどもこの説は、まだ焦の字の意味が明確になっておらず、また脂膜の説もまだもう一歩踏み込みが足りません。
その表裏の相配につては、すなわち三焦は臓腑の外衛であり、心包絡は心の外衛であって、これは帝闕〔伴注:宮門〕の重城のようなものです。ですからともに陽に属し、相火と名付けられています。またその脉絡は、もともと相通じているものであり、まさに表裏をなすものです。《霊枢・経脉篇》には、『心主は手の厥陰の脉、出て心包絡に属し、膈を下り、三焦を歴絡します。手の少陽の脉は、散じて心包を絡い、心主に合します』とあり、また、《素問・血気形志篇》には、『手の少陽と心主とは表裏をなします。』とあります。これはもとより明確なことであって、簡単に反論できるものではありません。
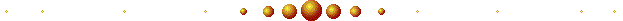
客が言われました。三焦は心主と表裏をなすとありますが、なぜ、さらに、命門と三焦とが表裏をなすという説があるのでしょうか?
いわく。三焦は包絡と表裏をなします。これは《内経》における一陰一陽の定偶〔伴注:定まって組み合わせ〕です。初めには命門との表裏の説はありませんでしたし、また命門という名前もありませんでした。ただ《霊枢・根結》《衛気》それに《素問・陰陽離合》といった篇には、『太陽は至陰に根ざし、命門に結します。命門は目です。』とあります。これは、太陽の経穴が睛明に終わるということを指しており、睛明が位置する場所が脳心〔伴注:脳の中心〕であり、これが至命の場所〔伴注:生命にとってたいせつな場所〕であるために、命門と言っているものです。これ以外に、腎を左右に分けるという説はなく、また右腎を命門とする説もありません。
命門の始まりは《三十六難》からです。『腎に二つありますが、その両方が腎なのではありません。その左にあるものを腎とし、右にあるものを命門とします。 命門は諸神精の舎る所であり、原気の繋る所です。男子はここに精を蔵し、女子はここに胞を繋ぎます。 』と。王叔和はこの説にもとづいてついに、『腎と命門とはともに尺部に出ます』と述べることとなり、後世、とうとう命門と表裏に配されることになったわけです。しかし《内経》には実はこの説はありません。
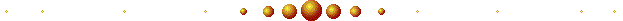
客が言いました。《内経》には命門の説がないのにどうして《難経》にはこの説があるのでしょうか?また命門の解釈は、結局はなんなのでしょうか?
いわく。《難経》の諸篇は皆《内経》から出ています。そうであるなら、この命門の解釈ももしかすると根拠があるかもしれません。意は古を去ることすでに遠く、経文に脱誤がないともかぎりません。七難に滑伯仁〔伴注:滑寿:一三〇四年~一三八六年〕が注しているように。【原注:滑伯仁は七難に注して、『首篇には経言の二字があります。これを考えてみるに、霊素には所見がありません。しかし越人の時代には、別にいわゆる上古の文字があったのではないでしょうか?内経においては、後世、脱簡があったのではないでしょうか?このことは知ることはできません』とあります。】ただ、右腎を命門とし、男子は精を蔵するとしていますが、それでは左腎は何を蔵しているのでしょうか?女子は胞を系るとしていますが、胞はどうやってただ右腎だけに系るのでしょうか?このことに疑問を持たないわけにはいきません。私は、歴代の諸書を考えてみました。《黄庭経》〔伴注:道教の経典:外景経と内景経とがあり、外景経は西暦四〇〇年頃の作と考えられ、内景経はそれをまねて西暦一〇〇〇年頃に作られたと考えられている。内観によって神を視、五臓を安定させることを説いています〕には、『上に黄庭〔伴注:一般には脾:ここでは目とし道の父母であると務成子は注しています〕があり、下に関元があります。後ろに幽闕〔伴注:腎:目と臍で連なると務成子は注しています〕があり、前に命門があります。』とありさらに、『命門を閉塞させれば玉都のようです』〔伴注:命門をしっかりと閉ざしていると、美しい都のようである〕とか、『丹田の中は精気微、玉房の中は神門の戸』〔伴注:丹田の中は精妙微細な精気のようであり、子宮の中は神の門の扉のようである〕とあります。梁丘子〔伴注:唐代の人〕は『男は精を蔵し、女は血を約す。ゆえに門戸という。』と、これに注しており、さらに『関元の中は男子が精を蔵する場所です。』とも述べています。元陽子は、『命門は下丹田にあり精気の出入りする場所です。』と述べています。これらの言葉は医家がまだ述べていなかった言葉で、ここにおいて初めて明らかにされたものです。
また《脉経》には、『腎は膀胱で合して腑となり、下焦に合し、関元の後ろに位置し、左を腎とし、右を子戸とします。』とあり、また、『腎は胞門子戸と名付けられ、尺中が腎の脉です。』とあります。この言葉は、右が子戸であるということは、すなわち、右が命門であるとした説です。いわゆる子戸とは子宮のことで、玉房の中のことです。俗に子腸と名付けられ、直腸の前、膀胱の後ろに位置し、関元と気海の間にあたります。男の精、女の血はともにここに存在し、子供はこれによって生まれます。ですから子宮とは実は、男女共にこう呼ばれているものなのです。
道家は先天の真一の気をここに蔵して、九還七返〔伴注:道教における内観の修行のことか〕の基とするため、これを丹田と名付けています。医家は衝任の脉がここに盛んであれば、月経が順調におこるために、これを血室と名付けています。
葉文叔〔伴注:不明〕は、『人が生を受ける初めには、胞胎の内に位置し、母の呼吸にしたがって、気を受けて成長します。生まれ落ちてからは、一点の元霊の気が臍下に集まり、自分で呼吸するようになります。気を呼する〔伴注:吐気〕ときは天根に接し、気を吸する〔伴注:吸気〕ときは地根に接します。人が生まれるということは、気を先としますので、名付けて気海といいます。』と述べています。このように、名前は異なりますが、実はこれはただ子宮のことを言っているだけのことなのです。子宮の下には一つの門がありますが、これは女であれば手で探ることができます。これを俗人は産門と名付けています。男であれば精を泄らす時に自身で知覚することができます。
これがどこであると思われますか?
客が言われました。それが命門なのでしょうか?
いわく。その通りです。もう一度詳しくお話ししましょう。
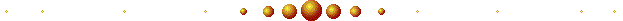
人の身体ができる前、父母が交接している時には、男が施すものはこの門から出、女が摂るものはこの門から入ります。胎が充分充実してくると、ふたたびここから出ます。出るのも入るのもこの門を通っているわけですから、これが先天立命の門戸でなくていったいなんでしょうか?
生まれ落ちてからは、三焦の精気はみなここに蔵されます。そのゆえに《金丹大要》には、『気が集まれば精が満ち、精が満ちれば気が盛んになる』とあり、梁丘子は、『人の生はその命を精に系る』といい、《珠玉集》には、『水は三才の祖、精は元気の根』と述べられているのです。ですから当然、精が去れば気が去り、気が去れば生命が去ることとなります。固めるのも去るのも、すべてこの門によります。これが先天立命の門戸でなくていったいなんでしょうか?
さらに《四十四難》を見ると、『七衝門』というものがあげられていて、これは皆出入りする場所のことを言っています。ですから、出入りするところはみな、これを門というのです。中でもこの一門は最も大きいものですので、名前を与えられていないということがあるでしょうか?これが命門でなければどこに属するものなのでしょうか?ここが命門であると理解できれば、男の蔵精・女の系胞はともにここに帰着することとなり、千古の疑問も一気に氷解していきます。
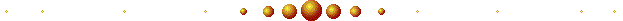
客が言いました。もしそういうことであれば、命門は右腎ではなく、子宮であるということになり、さらに一腑を別に設けることになります。これは何経に配されるのでしょうか?またこの脉はどこに出るのでしょうか?
いわく。十二経の表裏は陰陽によってしっかり配され、すでに定まっています。もし命門を再び一経として配すると、腎臓は一つであるにもかかわらずその経は二つあるということになり、理がまったく通らなくなってしまいます。また、命門は子宮の門戸であり、子宮は腎臓が精を蔵する府です。腎臓は先天真一の気であり、北門鎖鑰〔伴注:北門を閉ざす鎖錠:北方の重鎮〕を司るものです。それが鎖鑰である理由は、まさに命門が固く閉ざされることによって、坎中の真陽が蓄えられ、一身の生化の原となるためなのです。このように命門と腎とはもともと同一の気です。
道経ではこれを上下左右の真中にあたるとし、その位を極〔伴注:北極星〕に象り、名付けて丹田としています。丹は奇です。ですから北方を統括する天一の臓であり、その外兪は命門一穴であり、これはまさに督脉十四椎の中にあります。このように命門はもともと腎に属するものであり、別に一腑をなすものではありません。
《三九難》にもまた、『命門は、その気は腎と通じている、』とあります。これもまた腎と離れることはないということを言っているだけのことです。ただ、五臓にはそれぞれ一つあるだけなのに対して、腎だけには二個あります。二個あるということ自体はその象として特殊なことではありません。たとえば、耳や目は一つですが左は右よりも敏感であり、手足は一つですが、右は左よりも強いものです。このように、北方の神には蛇武があり、蛇は陽を主り武は陰を主ります。両尺の脉は左右に分けられ、左は水を主り右は火を主ります。左が陽で右が陰であるということは理の常です。
しかしここで左が水で右が火であるというのはどういうことなのでしょうか?腎は子の中に属し、その気は冬至に対応しています。これはまさに陰陽中分の位〔伴注:陰から陽へと天の気が移る時期〕にあたります。冬至以降は天は左旋して時は春となります。斗杓〔伴注:北斗七星の柄の部分〕は析木〔伴注:星宿の名前〕に建ち、日月は右行して合して亥〔伴注:の位置〕にあり、辰に次いで娵訾〔伴注:星宿の名前〕に会します。このように陽が一月進むと、会する場所は一宮退いて、太陽は徐々に右に行きます。
人もまたこれに対応しているため、水の位の右を火とするのです。また、人の四体は、もともと地に対応しています。地の剛は西北にありますので、右尺が陽であることも理の当然といえるでしょう。ですから、《脉経》では、腎臓の脉を両尺に配し、左尺を腎中の真陰を主るものとし、右尺を腎中の真陽を主るものと述べているのです。また命門は陽気の根ですから、三焦相火の脉も同じく右尺にあらわれるとすることも可となるのです。もし左腎は腎であるといい右腎を命門であるとするのであれば、これは間違いということになります。
しかしながら、もし分けてこれを言うならば、すなわち左は水に属し、右は火に属して、命門はまさに右尺に付くということになります。合してこれを言うならば、命門は北極星に象られ、消長の枢紐となります。左は昇を主り、右は降を主り、前は陰を主り、後ろは陽を主ります。ですから水の象は外が暗くて内が明るく、坎卦は内が「奇」で外が「偶」なのです。腎に二つあるということは、坎の卦の外側の「偶」のことです。命門の一は、坎の卦の真中の「奇」のことです。この一で二を統括し、二で一を包んでいるわけです。これは命門が両腎を総主しており、両腎はともに命門に属すということですので、命門は水火の府であり、陰陽の宅、精気の海、死生の竇〔伴注:門〕となるのです。
もし命門が虚損すれば、五臓六腑はみなその恃む場所を失い、陰陽の病変が至るところに発生することになります。その理由は、まさに天地発生の道は下に終始し、万物盛衰の理は、充実するも虚するもその根にあるからです。
このゆえに許学士〔伴注:許叔微:許知可:一〇七九年~一一五四年〕は、ただ補腎だけに着目し、薛立齊〔伴注:薛己:一四八六年?~一五五八年〕はいつも命門を重視したのでした。この二賢の高い見識は、はるかに常人を超えており、王太僕〔伴注:王冰〕のいわゆる『壮水の主、益火の原』を踏まえたものとなっています。これはまことに性命の大本です。医でありながらこれを知らなければ、何を理解しているというのでしょうか?この故に私はこれを明きらかにし、その義を広く用いられるようにしたのです。
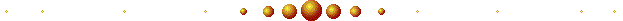
この篇の前後の諸論については、臆見も多いのですが、経文の意味をことごとく考えに入れたもので、敢えて妄言をなしたものではありません。私と心を同じくする方々のご批判をいただければ幸です。
2001年 6月3日 日曜 BY 六妖會